 |
平成21年度 神崎郡歴史民俗資料館講座録集 |
|
 ≪平成21年度連続講座≫ ≪平成21年度連続講座≫
「地域の歴史遺産は身近なところに」
~郷土への誘い~
| 開 催 日 |
講 座 名 |
講 師 |
場 所 |
時 間 |
| 第1回 |
5月23日(土) |
「銀の馬車道」と交流の拠点~福崎~ 済 |
足立裕美子氏
(兵庫県建築士会ヘリテージ
特別委員会委員) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第2回 |
7月18日(土) |
福崎の近昔物語-「鷺城新聞」の紙面から- 済 |
埴岡真弓氏
(播磨学研究所 研究員) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第3回 |
9月19日(土) |
三木家からみる播磨・福崎~人々の交流~ 済 |
河野未央氏 |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第4回 |
11月7日(土) |
おかげ参り・おかげ踊り・ええじゃないか 済 |
松井良祐氏
(県立考古博物館 学芸員) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
| 第5回 |
2月20日(土) |
再考・獅子が梯子を上るということ 済
-西播磨の事例から- |
大渡敏仁氏
(芸術文化学博士) |
歴史民俗資料館 |
13:30~15:00 |
 平成21年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集 平成21年度「播磨の歴史・民俗行事を考える」講座録集
<第5回 講座録>
日 時:平成22年2月20日(土) 13時30分~15時
演 題:再考・獅子が梯子を上るということ-西播磨の事例から-
講 師:大渡敏仁氏(芸術文化学博士)
2月20日、歴史民俗資料館にて、第5回目の連続講座を開催しました。
今回は、‘獅子どころ’として知られる西播磨の事例から、
毛獅子を中心とした、獅子舞の形態、囃子の特徴など、関連する映像とあわせて紹介いただきました。
近隣の事例を映像をとおして実際にみることで、迫力あるその姿や、
各地の芸態を知ることができ、普段目にすることのない細かなところに
着目することができました。
講座をとおし、改めて地域に根付く民俗行事のかけがえのなさや、
継承していく尊さ、そして記録していくことの大切さを実感することができました。
福崎町においても近年、獅子舞の囃子をもう一度再興させようと、取り組みがはじまったところです。
各地に伝わる獅子舞の姿と重ね、再び獅子が舞い音色が響く福崎での姿が目に浮かぶようでした。
本年度も様々な事例をとおして、郷土をみつめることができたことに感謝いたします。
また来年度もどうぞよろしくお願いします。
<第4回 講座録>
日 時:平成21年11月7日(土) 13時30分~15時
演 題:おかげ参り・おかげ踊り・ええじゃないか
講 師:松井 良祐氏(兵庫県立考古博物館)
11月7日、歴史民俗資料館にて、第4回目の連続講座を開催しました。
今回は、江戸時代大流行した、伊勢神宮への群集参拝である、
おかげ参りにはじまる民衆運動について、関連する資料とあわせて紹介いただきました。
一度は耳にしたことのある「おかげ参り」や「おかげ踊り」。そして「ええじゃないか」。
講座では、この「おかげ参り」にはじまる民衆運動について一連の流れや、
県内で確認されている関連資料、そして町内ゆかりの文化財など、
全体的なお話を聞く大変貴重な機会となりました。
これらが社会事象となるまでに流行した、当時の時代背景や、
実際に関連する資料をみることで、よりイメージを膨らませることができ、
当時の民衆のエネルギーをより身近なものとして感じることができました。
町内ゆかりの文化財の1つは、現在資料館で開催している特別展でも
展示されており、講座を聞いてからもう一度展示室へ足を運び、
資料を見ることで、また違った視点で資料をお楽しみいただけたのではないでしょうか。
これからも講座をとおして、郷土ゆかりの文化財をより身近なものとして感じていただければ幸いです。
次回は本年度最後の講座になりますが、
どうぞお気軽にご参加ください☆
<第3回 講座録>
日 時:平成21年9月19日(土) 13時30分~15時
演 題:三木家からみる播磨・福崎~人々の交流~
講 師:河野 未央氏(神戸大学大学院人文学研究科地域連携センター)
9月19日、歴史民俗資料館にて、第3回目の連続講座がはじまりました。
今回は、江戸時代大庄屋をつとめた、三木家住宅の当時の姿について、関連する資料とあわせて
ご紹介いただきました。
講座では、当時とのような政治や地域の流れがあり、その中で三木家がどのように位置づけられて
いたのかを知ることができました。
また、当時の生活の様子が、現代とも共有できるようなエピソードなどもあり、
三木家住宅について、改めて知る一面や、より身近なものとして興味・関心を高めることが
できたのではないでしょうか。
現在、三木家住宅は建物の老朽化が進み、その改修工事が迫られています。
講座をとおして、地域に残る歴史文化遺産のかけがえのなさとともに、
後世へと伝えていく重要性を、改めて考えることができた講座でした。
また、今後も三木家住宅のおもしろさを見つけていければと思います。
次回も、町内に関連する文化財がテーマである「おかげ参り」についてです。
ぜひお楽しみ☆
<第2回 講座録>
日 時:平成21年7月18日(土) 13時30分~15時
演 題:福崎の近昔物語-「鷺城新聞」の紙面から-
講 師:埴岡 真弓氏(播磨学研究所研究員)
7月18日、歴史民俗資料館にて、第2回目の連続講座がはじまりました。
今回は、明治に発行された「鷺城新聞」に掲載されている、当町の文化財情報について紹介いただき
ました。
再び「新型インフルエンザ」のニュースが舞い込む中での、講座開催でしたが、
今回も無事、先生をお招きすることができ、貴重なお話をいただくことができました。
当地域にゆかりの深い、「鷺城新聞」ではありますが、
その紙面に書かれていたことを知る機会は、意外と少ないのではないでしょうか。
講座では、貴重な当時の紙面をみなさんと見ていき、
様々な記事の中から、当町ゆかりの身近な文化財や、記念誌号に寄せられた柳田國男や
井上道泰の祝電なども見つけることができました。
また、当時の新聞に書かれている表現から、いつの時代も
文化財の発見は興味と関心を高めるものだということを共感することができました。
そして、当時紙面に載っているものが、現在でも郷土に残り伝わっていることで、
つながりを感じることができ、郷土においてとても大切なものだと再認識できたのではないでしょうか。
講座をとおして、新たな一面を探すことができた講座でした。
次回は、当町辻川界隈にある三木家住宅のお話です。
ぜひお楽しみ!
<第1回 講座録>
日 時:平成21年5月23日(土) 13時30分~15時
演 題:「銀の馬車道」と交流の拠点~福崎~
講 師:足立 裕美子氏(福崎町文化財審議委員会・兵庫県文化財保護指導員・兵庫県建築士会ヘリテージ特別委員会委員)
5月23日、歴史民俗資料館にて、本年度第1回目の連続講座がはじまりました。
開催にあたっては、「新型インフルエンザ」の影響が懸念されましたが、
無事先生と皆さんをお迎えすることができました。
今年は、「地域の歴史遺産は身近なところに」をテーマに、私たちの住む地域の文化財について
みなさんと一緒に考えます。
今回は、当地域にも関わりが深く、近年注目を浴びている「銀の馬車道」についてお話いただきました。
本講座では、生野銀山と「銀の馬車道」の歴史的な背景についてや、
兵庫県下で活躍する、歴史文化遺産の保全・活用を図るために調査や指導を行っている、
「兵庫県ヘリテージマネージャー」の活動をご紹介いただきました。
また、「銀の馬車道」沿線に関連する歴史的建造物についてや、資料館の建物である、
旧神崎郡役所の当時の姿を、古写真などでたどることができました。
本講座をとおして、「銀の馬車道」が地域においてかけがえのない歴史文化遺産であり、
まちづくりへと活かされています。
これらは、地域と地域とを結ぶとともに、人と人とを結ぶものであることが、
魅力の1つなのではないかと実感することができました。
次回は、明治に発行された「鷺城新聞」に掲載されている、
当町の文化財情報について、ご紹介いただきます。
ぜひまた講座へお越しください。
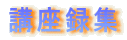
 平成20年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成20年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成19年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成19年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成18年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成17年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集 平成16年度「播磨の民俗と行事を考える」講座録集
◆問合せ先◆
神崎郡歴史民俗資料館
℡:0790-22-5699
※お問合せ・お申込みは資料館まで。 |
|
 |
|
|
